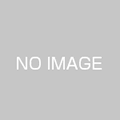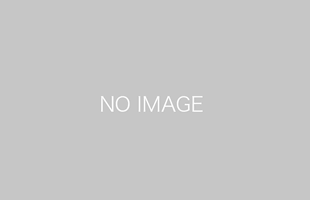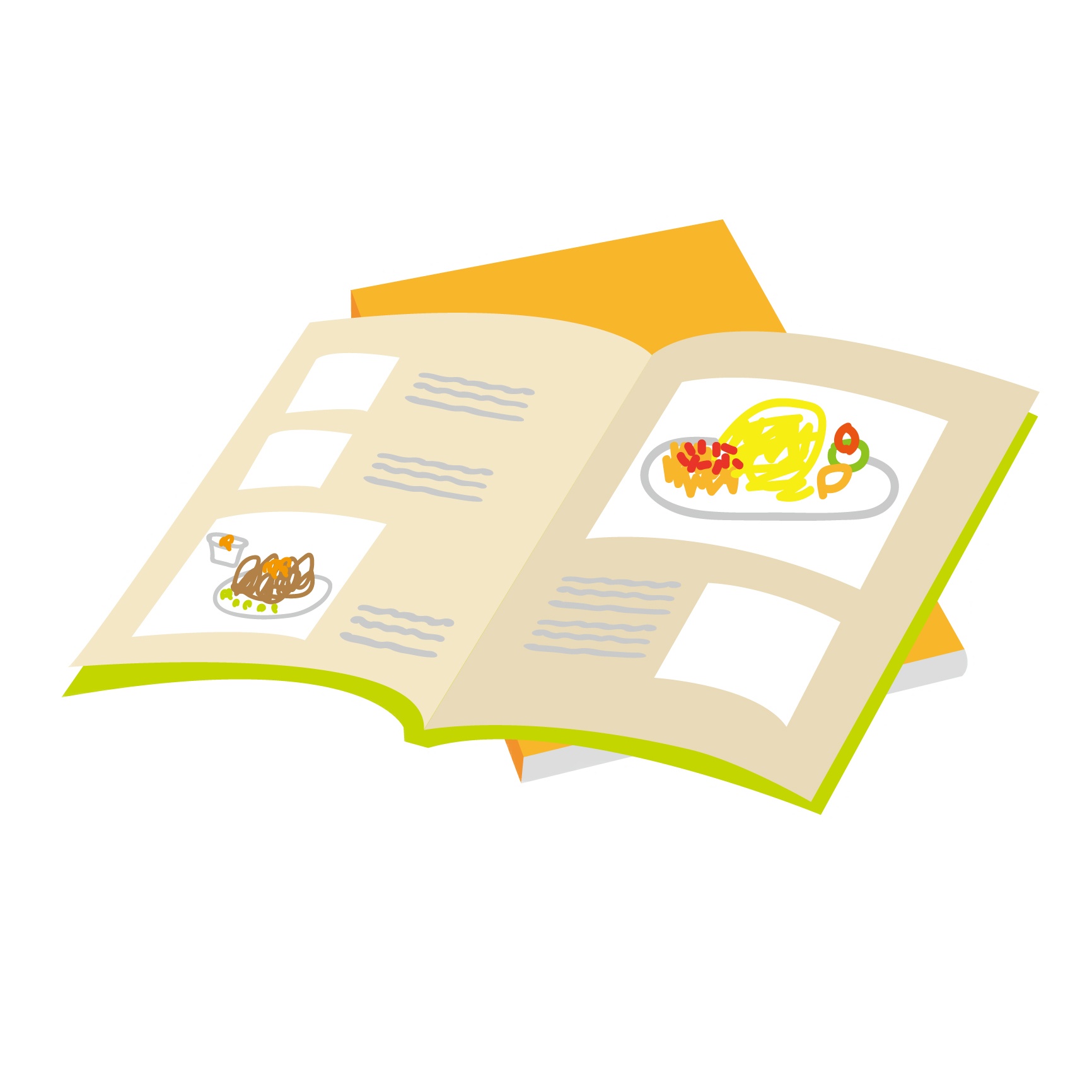発芽玄米の作り方は、専用の道具も、面倒な手間も、特別な環境もいりません。
とても簡単です。
事前に用意するものは、ザルとボウルと、あとはもちろん玄米だけです。
手順もシンプルで、
①玄米を洗う
②ザルにあけて水を切る
③ザルごとボウルの水に浸して放置する
④芽が出たらザルから上げて、あとは炊くだけ!
えっ、それだけ?と思うほど、発芽玄米の作り方って簡単ですよね。
だんだん習慣になってくると、もっと自分に合った作り方が見つかるかもしれませんが、まずはこの超簡単な方法を試してみましょう。
目次
発芽に必要なのは水+酸素、あとは“待つ”だけ。
玄米を買ってきたら、軽く洗います。
埃やごみなどを洗い流す程度でいいです。
洗ったらザルにあけ、ザルごとボールに入れます。
玄米が十分に浸るくらいの水、又はぬるま湯を注ぎます。
なぜザルを使うのかというと、ボールにそのまま玄米を入れるより、水や酸素がまんべんなく行き渡るので、均一に発芽しやすくなります。
玄米が発芽するのに必要なのは水と酸素だけです。
あとは、玄米の発芽する力にまかせて、待つのみなんですね。
冬だと だいたい2~3日、夏は半日~1日で発芽します。
ただ、夏場など匂いや雑菌の繁殖が気になるときは、途中で1、2回水を替えたり、2日目から冷蔵庫に入れれば大丈夫です。
どうなれば発芽状態?発芽した後の保存方法は?
ところで、どんな風になれば発芽玄米は完成なのでしょう?
だいたい0.5~1ミリくらい芽が出ればOKです。
全ての粒が発芽している必要はありません。
これで、自家製の発芽玄米の出来上がりです!
発芽玄米ができたら、水から上げましょう。
このとき、発芽が進行しすぎると まずくなるし、栄養価も減ってしまうので要注意です。
発芽玄米を炊いてみる
では、いよいよ炊飯器で炊いてみましょう♪
手作りの発芽玄米は 水分をたっぷり含んでいるので、白米と同じ水の量で炊けます。
すぐに炊かない場合は、タッパなどに入れて冷蔵庫で保管してください。
一週間くらい保ちます。
手作りの発芽玄米が続けられない理由
ただ、この基本的な作り方は、ちょっと不便なところがあります。
確かに手間はかかりませんが、出来上がるタイミングがはっきりわからないのが難点です。
なぜかというと、発芽の速度は気温に左右されるからです。
つまり、暑い日は早く出来て、寒い日は時間がかかる。
となると、計画的に作れないし、外出していたら発芽しすぎて、もやし状態になっていた!なんていう事も…。
特に冬場など、3日前に仕込まなければなりませんから、ちょっと煩わしいですよね。
これが、手作りの発芽玄米があまり続かない理由です。
待つのが面倒!失敗したくないなら?
作り方は簡単なのに、出来あがりが不規則だから諦める…。
それも、ちょっと惜しいですよね。
何とか発芽玄米を購入せずに作る方法はないのでしょうか?
じつは、“発芽玄米炊飯器”というのがあるんです。
炊飯器といっても「発芽玄米が炊ける炊飯器」というだけのものではありません。
玄米を計画的に、短い時間で発芽させることが出来るんです。
どうして、それが可能なんでしょうか?
玄米が発芽するまでの時間は、気温に左右されるという話をしましたが、発芽玄米炊飯器は、お釜の中の温度をコントロールします。
玄米が発芽するのに最適な温度というのがあって、その温度をずっとキープできるから、計画的に短時間で発芽させる事が出来るんです。
発芽までにかかる時間は、夏が4時間、冬は6時間です。
さらに、発芽→炊飯→保温まで全自動でやってくれます。
こうなると、手間も、コストも白米と変わらないですよね。
それでいて、おいしくて栄養価のUPしたお米を、毎日食べられます。
なんといっても主食は健康への影響が大きいですし、継続して初めて効果が得られるものです。
無理のない方法を選ぶのが、賢い選択かもしれませんね。
発芽玄米には不向きな玄米もある?玄米の選び方
玄米を購入するときは、“天日干し”と表示のあるものを選ぶのがベストです。
なぜかというと、玄米の中には機械で高温乾燥され、その熱で発芽する力が無くなってしまったものがあるんです。
ただ、“天日干し”の表示が無いものは全て発芽しないという訳ではありません。
試しに少量で購入して、実際に発芽実験してみるのが確実ですね。